The government and citizens' reaction to COVID19, in NZ 2
- cogy.net
- May 24, 2020
- 4 min read
ロックダウンの現実




スーパーマーケット:
ー1グループにつき一人だけが代表で買い物をする
ー入店数を制限するため行列ができる。
ースーパーの入り口から、2メートルごとに線が引いてあり、これに従って並ぶ
ー医療関係者など、essential workers は、制服やIDカードなどを示して、並ばなくても入れる。
ーある日の朝、スーパーの開店10分前に行ったところ、すでに行列が500mできていた。
ーレジでは、隣の列との間にプラスチックの壁
ーチェックアウト・オペレーターと客の間にもプラスチックの仕切り
ー現金ではなく、カードを使うことを推奨される
ー床に丸が描いてあって、計算してもらっている間は、ここで待つ。オペレーターと距離を保つため
ーオンラインで注文して、鍵付きロッカーからピックアップするサービスもあるが、二週間先まで常に予約で満室。


薬局:
ー入店数を制限
ー2m間隔で列を作って待つ
ー入り口に、薬局スタッフとセキュリティスタッフ(たいていの場合、大柄、男性、強面)が待機。彼らはマスクと手袋を着用している。
ー処方箋目的かそれ以外かを聞かれる(その結果どう分かれるのかは不明)
ー表面温度計と思われるもので、非接触で検温(高いと入店を断られると思われる)。
ー中から一人出てくるのを待って、入店。

品揃え:
品切れになったのが、小麦粉、ベーキングパウダー、ベーキングペーパー。在宅時間が長くなるため、ケーキなどを焼くことで紛らわせようというのが、主流のよう。または、パンの買いだめをする代わりか。トイレットペーパーは豊富だった(ロックダウン一週間時点)






コンビニ:
デイリーと呼ばれる、昔の日本でいう駄菓子屋のような規模の店があり、スーパーに行くほどでもない場合はここで済ませる。24時間空いているわけではない。ここはロックダウン中も営業するが、店内にいる客数は、常に1または0でなければならない。また、必需品としてカテゴライズされないものは売ってもらえない(はず)。
文房具:
スーパーマーケット以外の店は、必需品に限り、オンラインで、配送でのみ営業できる。配送料も、普段より安く設定されている。その店のサイトに行くと、普段の商品一覧に「必需品認定」マークがあり、それがない商品は注文できない。在宅勤務が奨励されるため、ペーパーレスとはいえ、文房具は大切になる。
DIYショップ;
業者対応のため営業しているが、一般住民は利用を拒否される。
飲食:
店内飲食、持ち帰り、共に営業禁止。スーパーで買えるもので、できあいのものは、加熱しなければ食べられないものしか販売されない。
酒店:
スーパー内に酒コーナーがある場合は、仕切りがしてあり、同時に一人だけがそのコーナーに入れる。入り口で名前、住所、連絡先を記入する。一人につきXX品のみ、と購入数に制限がある。
自動車整備:
essential work にまつわるもののみ整備してもらえる。
通信:
幸いなことに、大きな問題は起きていない。最も電話が繋がりにくかったのはロックダウンに入る直前日。しかし、インターネットは機能しつづけたので、email で伝えた方が早い場合もあった。その後一週間経っても、電話は(使っていないのでわからないが、電話をよく使う人によると)繋がりにくい。
インフラ:
普段よりとてつもなく大量にインターネット回線が使われているはずなのに、ロックダウン中もめだった問題がないのは、事前にIT業者が準備していたのではないだろうか。他にも電気消費量は、時間と場所でみると相当量変化しているはずだが、供給が追いつかないといったニュースが無いことを見ると、これも準備してあったのだろうか。
教育業:
ほとんどがオンラインに移行。様々なソフトウエアが挙げられるが、会話の際の時間差が今までで最も少なかったのが、Zoom. ある大手スポーツジムは、公共テレビで毎日XX時にプログラムを放送、普段はメンバーだけがジムのフロアで参加するものだが、この際は誰もが無料で参加(視聴)できる。他にも、ブートキャンプなどグループ・フィットネスを行っていた業者は、これもzoom等で続行。これにあたり、課金する場合と、無料で提供する場合があるが、無料のケースが多い。また、普段はジムの備品を使用していたところ、ロックダウン中は家庭内で代用品を見つけねばならず、事前に準備品リストが告げられたりもする。
安否確認:
NZには語学等のための留学生が多い。家族から離れて異国でロックダウンを経験する生徒たちのために、学校側から毎日連絡を入れて安否確認をするとともに、会話を通じて精神衛生の保持につとめているようだ。
(レポート1、2、3)
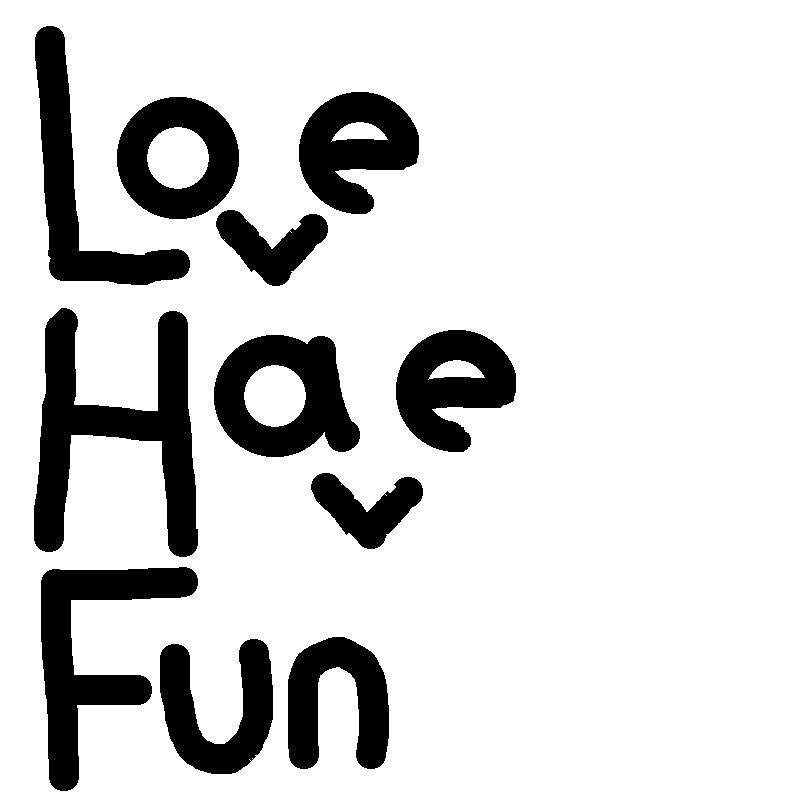

Comments